『理系技術者の「知財×経済」』にご訪問いただき、ありがとうございます。
本来なら初期の投稿は「知的財産って何?」や「知的財産と経済のかかわり」など、当ブログの基礎となるトピックを投稿しようと思いましたが、直近で知財に関わる大きなニュースが出ましたので、急遽こちらの話題を取り上げることにしました。今後も、このような注目のニュースには、臨機応変に素早く情報発信していきます。
さて、今回は、最近ニュースで大きく報じられた、東レ先発医薬品の特許侵害を取り上げます。私自身、製品開発の業務をこなす中で、開発の各フェーズで大量の他社特許に目を通します。多い時には1日200件以上。。。それだけ時間をかけても他社の先行技術を調査することは非常に重要であることが、今回の報道で再確認できました。
報道によると、賠償金額は約217億円にも上るとのこと。この新薬はかゆみ止めで、私も幼少期(今も少々)アトピーに悩まされたのでその点でも興味深いです。第一報ではこの注目の事件の「訴訟内容」にスポットを当てて、どのような点が争われたのか、詳しく見ていきましょう。
◆ 事件の当事者と、問題となった医薬品
まずは、本件に関わる主な企業と、キーアイテムとなる医薬品についてご紹介します。
東レは、「沢井製薬と扶桑薬品工業が販売しているジェネリック医薬品は、自社が保有する重要な特許を侵害している」と主張し、裁判所に訴えを提起しました。
◆ 特許制度の基本と、本件特許のポイント
ここで、簡単に特許制度の基本をご説明します。本来は先に「知的財産の基礎」カテゴリーで説明予定でしたが、今回はごくごく基礎に絞って記載しますね。
特許とは、新規な発明を保護するための権利です。特許庁に出願し、審査を経て認められると、一定期間、その発明を独占的に実施することができます。他者が無断でその発明を実施した場合、「特許権侵害」として法的措置を求めることが可能になります。
特許の内容で特に重要なのが**「特許請求の範囲」**(クレームとも呼ばれます)です。ここに記載された文言が、特許によって保護される発明の技術的範囲を画定します。今回の事件で問題となった東レの特許(特許第3531170号)は、「止痒剤(しかゆざい)」、すなわち「かゆみ止め」に関する発明でした。
この特許の「請求項1」には、概略として次のような内容が記載されていました。 「特定の化学構造(一般式(I))で表される化合物を有効成分として含有する、止痒剤。」
この「特定の化学構造で表される化合物」というのが、専門的には「ナルフラフィン(フリー体)」と呼ばれる物質を包含していた、という点が本件を理解する上での鍵となります。
◆ 「フリー体」と「塩酸塩」の違いとは?ここが最大の争点!
「ナルフラフィン(フリー体)」という言葉が出てきました。 今回の事件を理解する上で非常に重要なのが、この「フリー体」と、ジェネリック医薬品の有効成分である「ナルフラフィン塩酸塩」との法的な“同一性”です。
知財に馴染みのない方にもイメージしやすいように、料理に例えて説明してみましょう。
沢井製薬らは、「我々の医薬品は“下味処理を施した鶏肉(塩酸塩)”を使用している。東レの特許は“鶏肉そのもの(フリー体)”を対象としているのだから、構成が異なる。特許侵害にはあたらない」と主張しました。 これに対し東レは、「いや、体内に投与されれば結局“鶏肉そのもの(フリー体)”として薬理効果を発揮するのだから、実質的には同一であり、特許を侵害している」と反論しました。
この「有効成分」の解釈、つまり特許で保護されている「フリー体」と、ジェネリック医薬品で使用されている「塩酸塩」が、法的に見て「同一」と評価されるのか、それとも「異なる」ものとして扱われるのか、という点が、この裁判における最大の争点となったのです。
◆ 裁判の経過:第一審と控訴審で覆った判断
この争点について、裁判所はどのように判断したのでしょうか。
◆ 知財高裁の判断理由:「実質」を重視
知財高裁が特に注目したのは、**「医薬品が実際に体内でどのように薬理効果を発揮するか」**という点でした。 ナルフラフィン塩酸塩(下味処理を施した鶏肉)は、経口投与されると体内で「塩酸」部分が解離し、結果として「ナルフラフィン(フリー体)」(鶏肉そのもの)となって、この「フリー体」がかゆみを抑制する効果を発揮します。
知財高裁は、 「確かに医薬品の形態としては『塩酸塩』であるが、体内で薬効を発揮するのは『フリー体』であり、その薬理効果は東レの特許発明が保護しようとした核心部分に他ならない。したがって、実質的に見て、ジェネリック医薬品は東レの特許発明の技術的範囲に属する」 と判断しました。
つまり、特許請求の範囲に記載された「有効成分」という用語を、医薬品の承認書やラベルに記載された化学物質の名称のみで形式的に判断するのではなく、その医薬品が実際に体内でどのように作用して治療効果を発揮するのか、という「実質」を重視したのです。これは、医薬品特許の解釈において、非常に重要な判断と言えるでしょう。
また、この本訴訟と並行して、東レの特許の「存続期間延長登録」の有効性についても複数の訴訟で争われていました。医薬品は、開発から承認までに長期間を要するため、特許期間を一定期間延長できる制度があります。この延長登録の有効性を巡っても、「有効成分」の解釈が大きな争点となっていましたが、知財高裁はこれらの関連訴訟においても、東レに有利な判断を一貫して示していました。
【筆者の視点】
今回の判決は、医薬品特許の解釈に大きな一石を投じましたが、その波紋は私が専門とする化学業界にも及ぶ、きわめて重要なものだと捉えています。
記事で解説した「投与後に体内で有効成分に変わる」という話は、化学の世界では日常的な現象です。身近な例では、使い捨てカイロ(鉄の酸化)、電池(化学エネルギーの変換)、漂白剤(酸化還元反応)など、販売時の組成から化学反応を経て初めて価値を生む製品は枚挙にいとまがありません。
だからこそ、「出荷時の構成だけでなく、使用時の化学組成や作用機序まで含めて発明の実質的価値と捉える」という今回の司法判断は、私たち開発者にとって非常に大きな意味を持ちます。今後の開発プロセスでは、先行技術調査の段階で、これまで以上に「使用時の状態」を想定した多角的な特許分析が求められるでしょう。これは、開発戦略そのものを見直すきっかけにもなり得ます。
一人の開発者の視点から言えば、苦労の末に生み出された発明の本質的な価値が、形式的な文言解釈ではなく、その作用メカニズムという「実質」で評価された今回の判決を、心から歓迎したい気持ちです。
◆ まとめと次回予告
今回は、東レと後発医薬品メーカーとの間で争われた「かゆみ止め」薬の特許訴訟について、主に「何が争点だったのか?」という訴訟内容に焦点を当てて解説しました。
知財高裁が「形式よりも実質」を重視し、医薬品の体内での作用メカニズムを考慮して「有効成分」の範囲を解釈したことは、今後の医薬品特許実務に大きな影響を与える可能性があります。
さて、この判決、特に約217億円という巨額の賠償命令は、製薬業界全体や私たち消費者に、具体的にどのような「経済的な影響」を及ぼすのでしょうか? 次回は、その点を詳しく掘り下げていきたいと思います。ではまた!
(この記事は、公開されている情報を基に、知的財産に馴染みのない方にも分かりやすくお伝えすることを目的として作成しています。法的な解釈や詳細については、専門家の情報や公式な判決文等をご確認ください。)

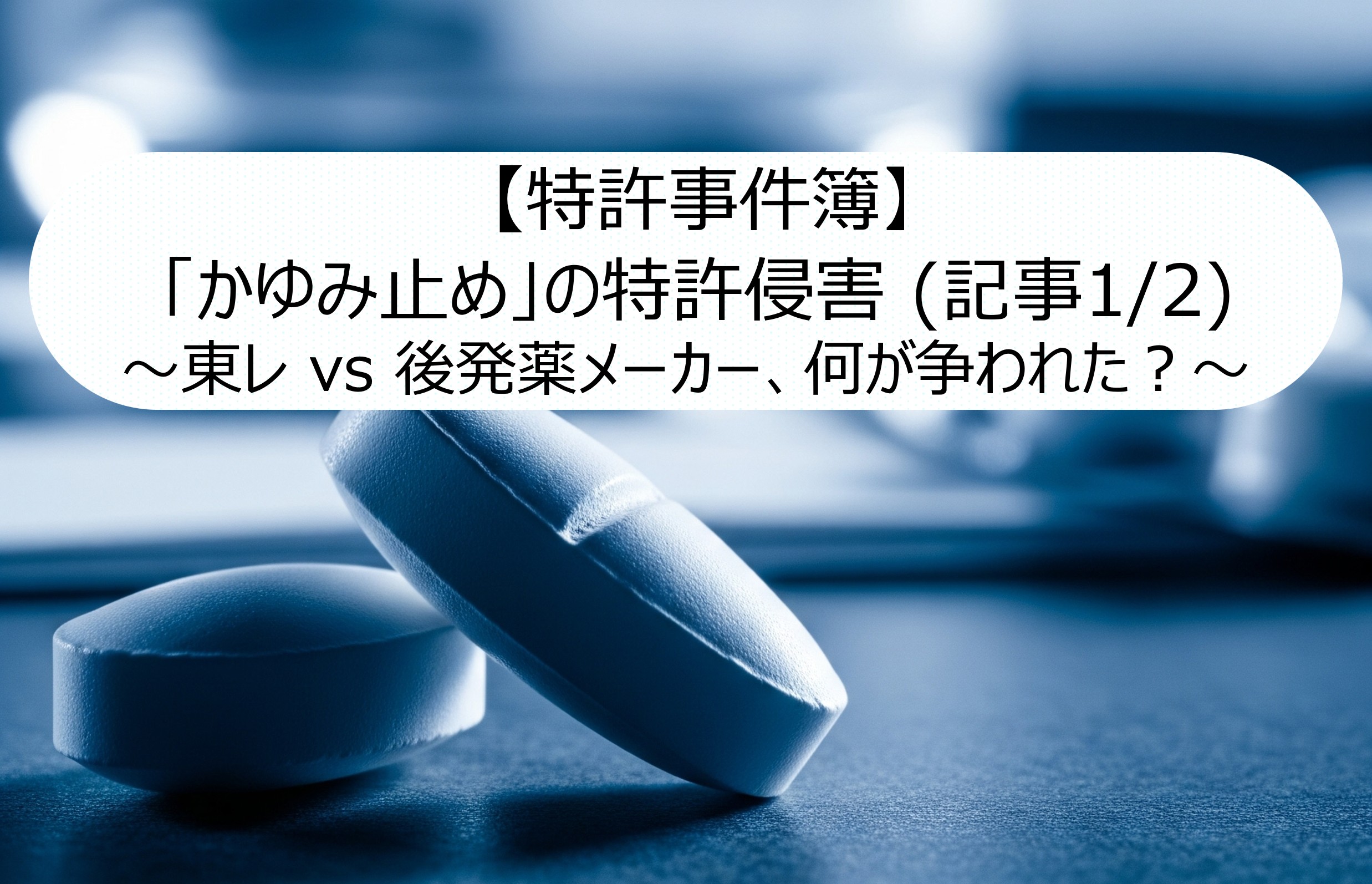


コメント