こんにちは!『理系技術者の「知財×経済」』の続編記事へようこそ。
前回の記事では、東レと後発医薬品メーカーとの間で争われた「かゆみ止め」薬の特許訴訟について、主な争点と知的財産高等裁判所(知財高裁)の判断内容を解説しました。前回記事はコチラ!
「有効成分」の解釈という、一見専門的なテーマでしたが、裁判所の判断が第一審と控訴審で大きく変わり、「形式」から「実質」を重視する方向へ転換した、非常に興味深い訴訟でした。私自身、開発業務におけるクリアランス調査に、作用後の組成や作用機構も厳密に確認するべきである事を再確認しました。
さて、今回はその続編です。 この裁判では、後発医薬品メーカーから東レに対し総額約217億円という、極めて高額な損害賠償が命じられました。この「217億円」という数字が、製薬業界や私たちの生活に、どのような「経済的な影響」を与え得るのか、私なりに解説してみますね。
◆ 217億円という賠償額、その内訳と意味
まず、改めて賠償額について確認します。 知財高裁が命じた賠償額は、
これを合計すると、約217億円に上ります。これは、日本の産業界全体で見ても、知的財産権侵害訴訟における高額な賠償事例の一つです。
では、なぜこれほど高額な賠償額が算定されたのでしょうか? 特許権侵害における損害賠償額の算定には、主に以下のような考え方があります。
- 特許権者の逸失利益: もし特許侵害行為がなければ、特許権者(東レ)が得られたであろう利益。
- 侵害者利得: 特許を侵害した者(沢井製薬など)が、侵害行為によって得た利益。
- 実施料相当額: 特許発明の実施に対し、通常得られるべきライセンス料に相当する金額。
本件では、東レの先発医薬品「レミッチ®」が一定の市場シェアを有していたこと、そして沢井製薬などが後発医薬品を販売していた期間(2018年から特許権の存続期間満了である2022年11月まで)の売上高や市場規模などを考慮し、東レが被った損害、あるいは沢井製薬などが得た利益が相当額に上ると判断された結果、このような高額賠償に至ったものと考えられます。
◆ 製薬業界へのインパクト:後発医薬品メーカーの戦略は変わるか?
この判決、とりわけ「217億円」という数字は、製薬業界、特に後発医薬品(ジェネリック医薬品)メーカーにとって、大きな衝撃となりました。
ジェネリック医薬品メーカーは、新薬(先発医薬品)の特許期間満了後、あるいは特許が無効と判断された後などに、同じ有効成分を用いた安価な医薬品を開発・販売することで、患者負担の軽減や国民医療費の抑制に貢献しています。
しかし、時には、先発医薬品の特許がまだ有効である可能性を認識しつつも、自社の製品は特許発明の範囲外であるとの判断に基づき、特許紛争のリスクを冒してでも早期に市場参入を図るケースがあります。これを一般に「アットリスクローンチ(at-risk launch)」などと呼びます。
今回の判決は、この「アットリスクローンチ」に伴う経営リスクがいかに甚大であるかを、改めて示すものとなりました。 「有効成分の形態がわずかに異なっていても、実質的に同一と判断されれば、巨額の賠償責任を負う可能性がある」という認識が、業界内で一層強まったと考えられます。
今後の影響として、以下のような変化が予想されます。
一方で、先発医薬品メーカーにとっては、自社が多大な投資を行って開発した新薬の特許が、より実質的かつ広範に保護される可能性が示されたと受け止められるかもしれません。これにより、研究開発へのインセンティブが維持され、革新的な医薬品の創出に向けた取り組みが継続されることが期待されます。
◆ 私たちの生活への影響は?:医薬品の価格や新薬開発の将来
では、この判決は、製薬企業だけでなく、私たち患者や社会全体に対してどのような影響を及ぼし得るのでしょうか?
この問題は多角的に考察する必要があります。
今回の判決が、直ちに私たちが利用する医薬品の価格に変動をもたらしたり、新薬の開発速度が急上昇するわけではありません。しかし、製薬業界全体の事業戦略や研究開発の方向性に影響を与えることを通じて、中長期的には私たちの医療環境にも関わってくる可能性がある、という視点は重要です。
【筆者の視点:開発者の喜びと社会との対話】
前回記事でも書いたように、一人の技術者として、私は今回の判決を嬉しく感じています。一つの革新的な製品が世に出るまでには、まさに血の滲むような研究開発の積み重ねがあります。その多大な努力と挑戦が正当に報われることは、さらなる技術革新への何よりの原動力となり、ひいては人類の進歩に貢献すると信じているからです。
しかし、同時に複雑な思いも抱いています。開発の現場にいるからこそ先発メーカーの努力が報われてほしいと願う一方で、一人の生活者としては、安価で質の高いジェネリック医薬品が普及することの恩恵も十分に理解しています。
この「イノベーションを守る価値」と「社会全体の利益」とのバランスをどう取るべきか。私たち開発者は、この両者の間に存在するある種のギャップを常に意識し、社会と対話するような姿勢で誠実にものづくりに取り組む必要がある。今回の判決は、そのことを改めて私に教えてくれました。
そして、もう一つ。今回の事例は、ごく当たり前のことですが、開発の根幹をなす特許クリアランス調査で決して手を抜いてはならないという基本を、これ以上ないほど明確に示してくれました。この戒めは、深く肝に銘じたいと思います。
皆さんは、この判決をどのように受け止められたでしょうか?
◆ 今後の展開:最高裁判所での審理は?
この訴訟は、まだ最終的な決着を見たわけではありません。 沢井製薬、扶桑薬品工業の両社は、知財高裁の判決を不服として、最高裁判所に上告する意向を表明しています。
最高裁判所は、法律解釈の統一や、下級審の判決に法令違反がある場合など、限られた場合にのみ上告を受理し、審理を行います。もし最高裁判所が本件を受理し、判断を示すことになれば、「有効成分」の解釈という、医薬品特許における極めて重要な論点について、最終的な司法的見解が示されることになります。その判断は、今後の日本の医薬品特許実務や、関連する産業界に、決定的な影響を与える可能性があります。
まさに、法曹界、製薬業界、そして経済界からも大きな注目が集まる展開となるでしょう。
◆ まとめ:未来の医療にも影響を与える可能性を秘めた判決
今回は、「かゆみ止め」薬をめぐる特許訴訟がもたらした約217億円という賠償命令と、それが経済や社会に与える可能性のある影響について考察しました。
一つの特許訴訟の判決が、これほどまでに大きな経済的インパクトを持ち、さらには私たちの生活にもつながる未来の医療のあり方にも影響を与え得る、ということを感じていただけたでしょうか。
「知的財産」と「経済」、そして「私たちのミライ」。このブログでは、これからも、このような視点から興味深いトピックを掘り下げていきたいと考えています。
次回からは、当初の予定通り「知的財産と経済のかかわり」のような、本ブログの本質的な部分について記事を書きたいと思っています。…が、もしかすると、本記事にもう一つ番外を追加するかもしれません(結局しました!)。いろいろと試行錯誤していきながら進めていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではまた!
(この記事は、公開されている情報を基に、知的財産に馴染みのない方にも分かりやすくお伝えすることを目的として作成しています。法的な解釈や詳細、経済への具体的な影響については、専門家の情報や公式な判決文等をご確認ください。)

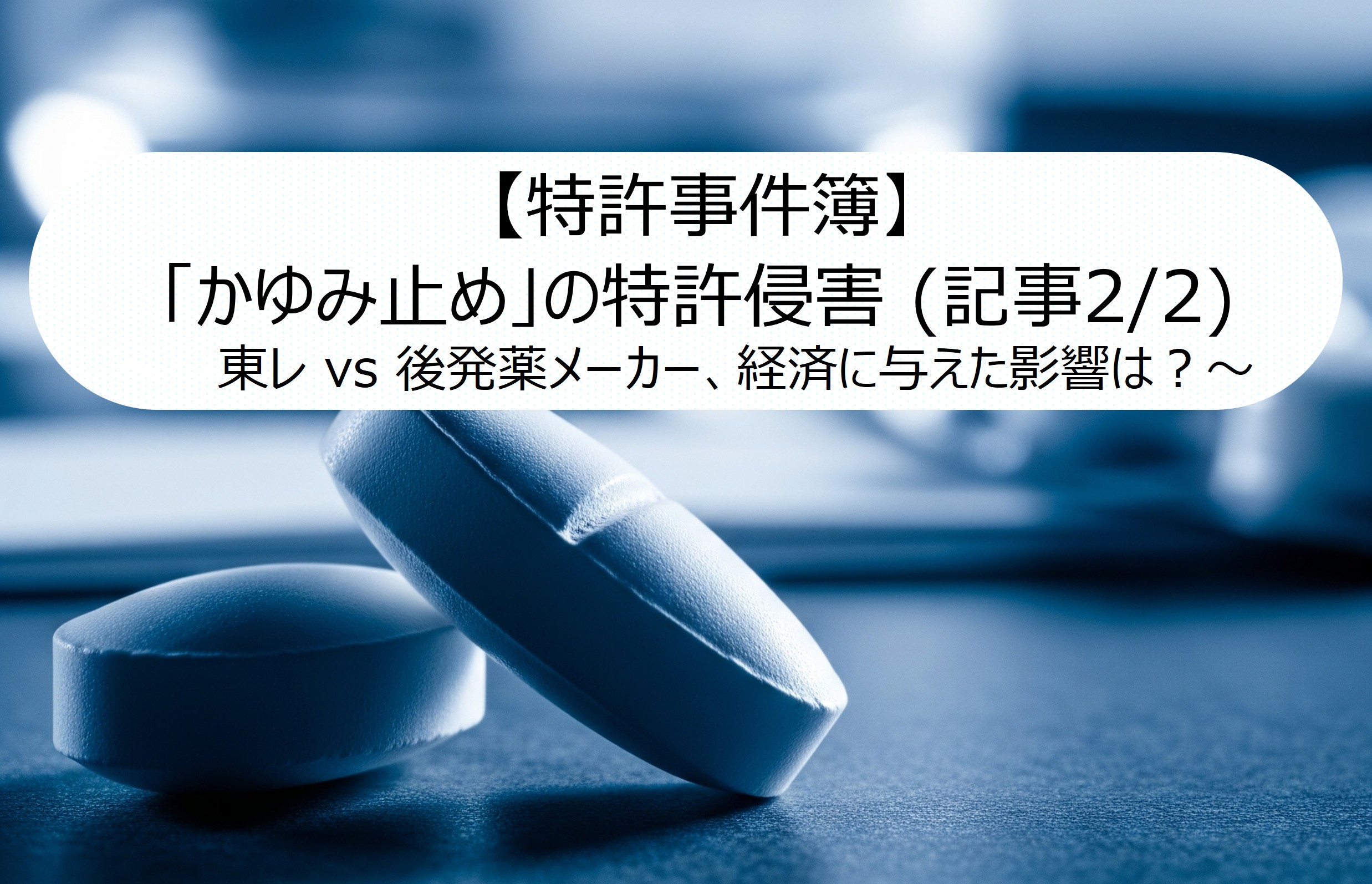


コメント